介護の孤独を和らげる、つながりの力
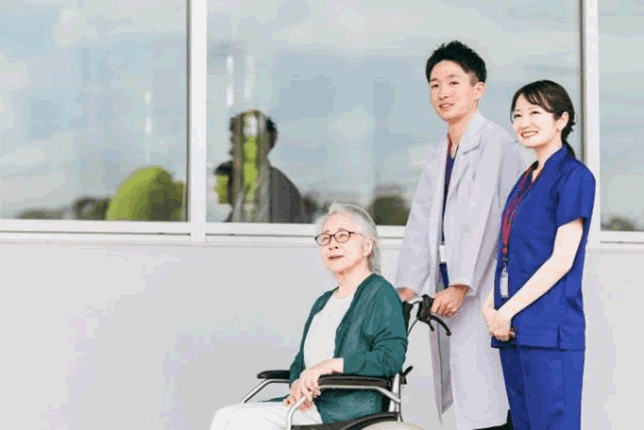
介護をしていると、孤独や悩みがつきものです。母親の介護と仕事の両立に苦しむ中で、支え合う大切さを実感したS.Kさんは、周囲とのつながりを大切にしながら介護を進めていきました。
その中で得た気づきや工夫を、皆さんにお伝えしたいと思います。
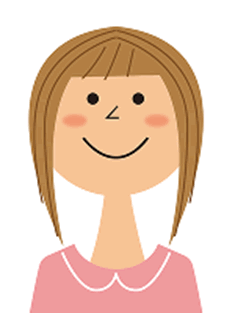
S.K(50代) 無職
家族: 母親と2人暮らし
要介護者:実母(同居)
服選びから通院まで、私たちの介護リズム
母と私の朝は、その日に着る服を一緒に選ぶところから始まります。ブラジャーは一人では着けにくいので、「手を上にあげてね」と声をかけて、無理のないように手伝うことが必要です。
気温や体調に応じて、服装や布団の厚さもこちらで判断します。温度調節が苦手になってしまったからです。暑すぎたり寒すぎたりしないように、こまめに様子を見ながら調節しています。お風呂上がりにはヒートショックを防ぐため、すぐに暖かい部屋へ移動してもらい、速やかに着替えを済ませるように。特に冬場は注意が必要です。
薬はどうしても飲み忘れが出てしまうので、毎月のチェック表を作成し、一緒に確認して服薬するように。母に薬を飲んでもらったあと、ひとつひとつチェック表に記入して、自分自身の「飲ませたっけ?」という不安を減らし、うっかり忘れの防止につなげています。
忙しい毎日の中でも、こうした確認を習慣にすることで、安心して介護に向き合えるようになりました。
また、通院の際は必ず付き添い、ケアマネジャーさんや医師に現在の状態を直接伝えています。本人だけでは伝えきれない部分を補うことができるので、これは大切なことです。
同じ話を繰り返したり、「そんなこと言ってない」と言われたりすることもあります。時にはわがままに聞こえることもありますが、その都度話を聞いて、「じゃあこうしようか」「それなら私がやるよ」と、なるべく穏やかに対応するように心がけています。
外出時には、ホワイトボードやメモを活用。その日に食べるものや食べ方を、大きな字で具体的に書いて、見やすい場所に置くようにしています。迷わず行動できるようにする工夫のひとつです。
通勤と家事と介護と…働くことに迷いが出たとき
仕事との両立については、正直とても悩みました。通勤してフルタイムで働くことや、介護のために休みを取ることがだんだん難しくなってきたからです。
というのも、母が家事のほとんどをこなせなくなってきたから。日常の中で私が家にいることが“当たり前”になっていき、料理や洗濯、ちょっとした用事など、誰かがそばにいなければまわらない状況で「仕事に行く」という選択そのものが気軽にはできなくなってしまいました。
当時働いていた職場はとても忙しく、介護を理由に休むことがまだ浸透していない雰囲気でした。「また?」という空気を感じてしまうこともあって、申し訳なさや居づらさが重なり、ますます言い出しにくくなってしまい…。気持ちの面でも大きな負担を感じていました。
頼ることは、弱さじゃない。私が実感した支え合いのかたち
母が要支援の段階だったころは、地域包括支援センターの担当の方と相談しながら、できる範囲で支援を受けるようにしていました。一人で抱え込まず、専門の方に間に入ってもらうことで、気持ちにも少し余裕が生まれるので、これから介護にあたる方は地域の相談センターを調べておくことをお勧めします。
仕事に関しては、職場でのストレスや悩みをひとりで抱え込まないように意識していました。キャリアコンサルタントの方や信頼できる同僚に話を聞いてもらうことで、少し気持ちが軽くなったことも多かったです。
母の通院に付き添う必要があるときは、なるべく早めに上司に伝えて、理解を得られるよう心がけていました。急な対応が必要になることもあるので、普段からこまめにコミュニケーションをとるようにしたことも、工夫のひとつです。
こうして外と関わりを持ち続けたことで、介護だけに閉じこもらず、社会とのつながりを保つことができました。それは、精神的にもとても大きな支えでした。自分自身の悩みに寄り添ってもらえていると感じられることが、気持ちを前向きに保つ助けになっていたのだと思います。
つながることから始めよう。介護の孤独に悩まされないために
私のまわりには、当時あまり介護をしている人がいなくて、気持ちを理解してもらえないと感じることも多くありました。だからこそ、ひとりで抱え込まず、相談できる人を見つけておくことが大切だと思います。
職場など、身近な環境の中で少しずつ話をして、理解を得られるよう努めることも一歩です。自分がどういう状況にあるのかを伝えることで、サポートや配慮を受けやすくなることもあると思います。
また、地域の見守り活動や介護事業所、自治会などを活用することで、思いがけない支えが得られることもありました。制度や地域のつながりを上手に使うことも、無理をしないためのひとつの方法ですよ!
ぜひ、周りのサポートを上手に活用してほしいと思います。すべてを背負う必要はありません。心や体の負担を軽くする方法はきっと見つかります!


